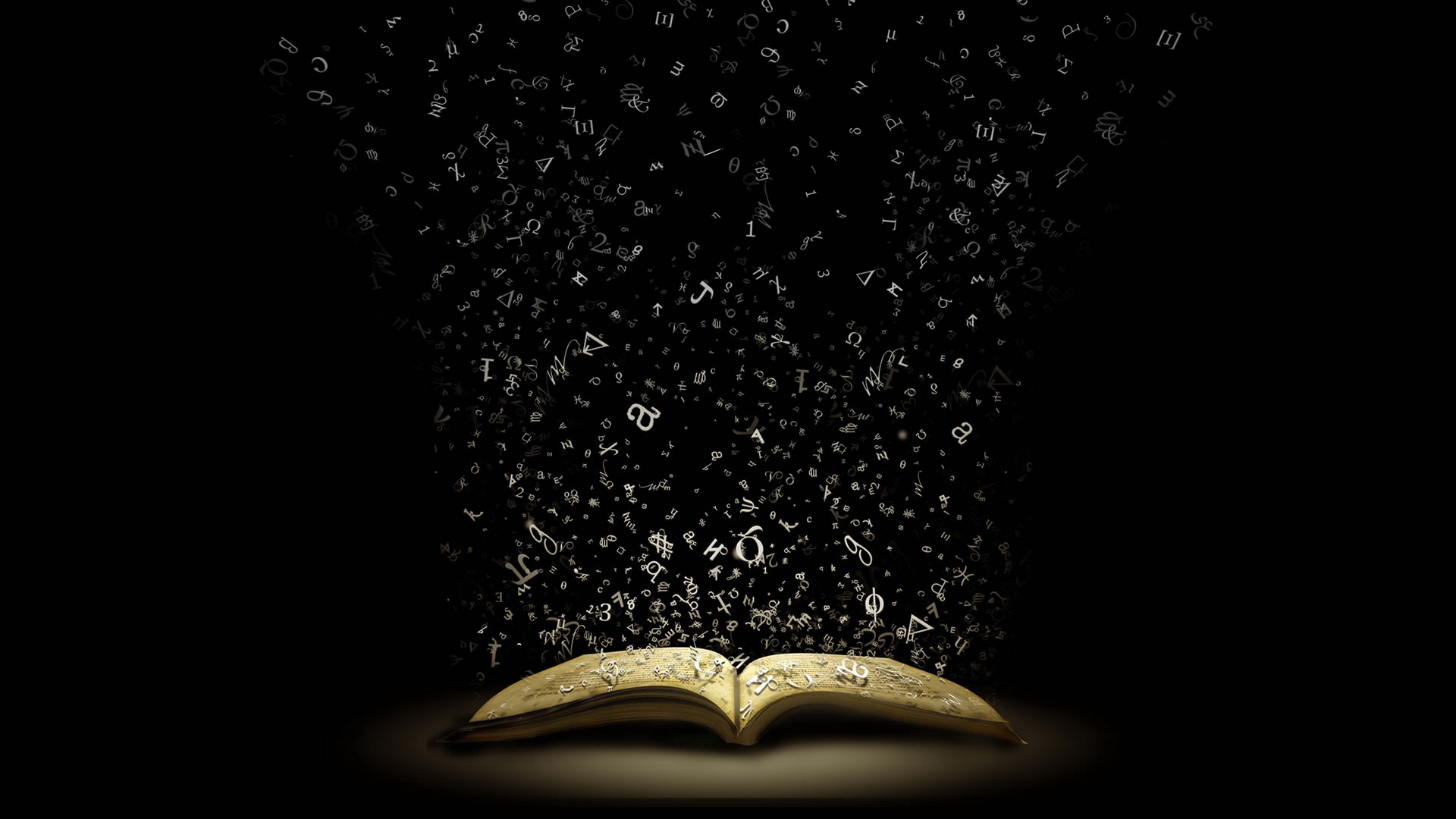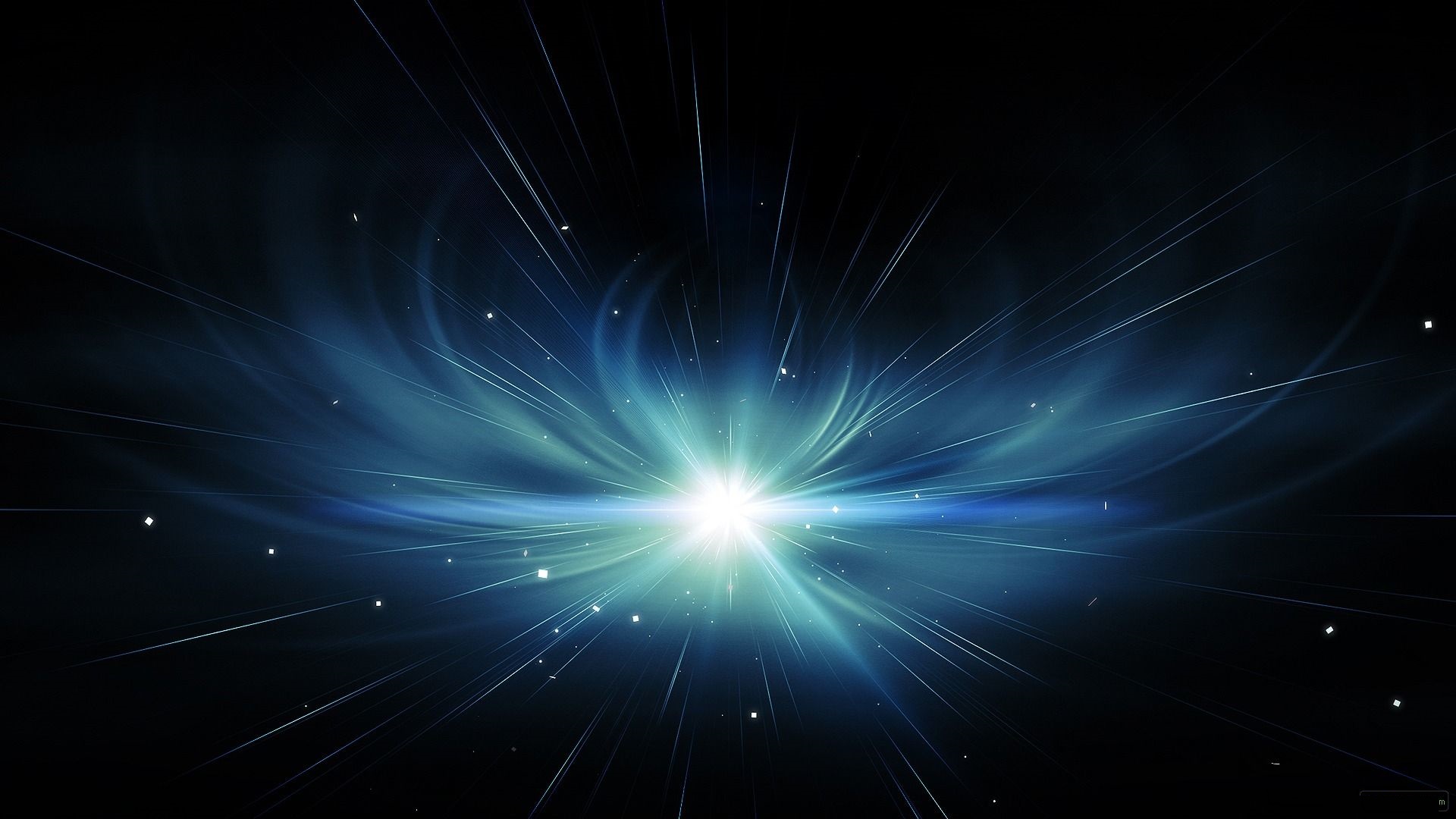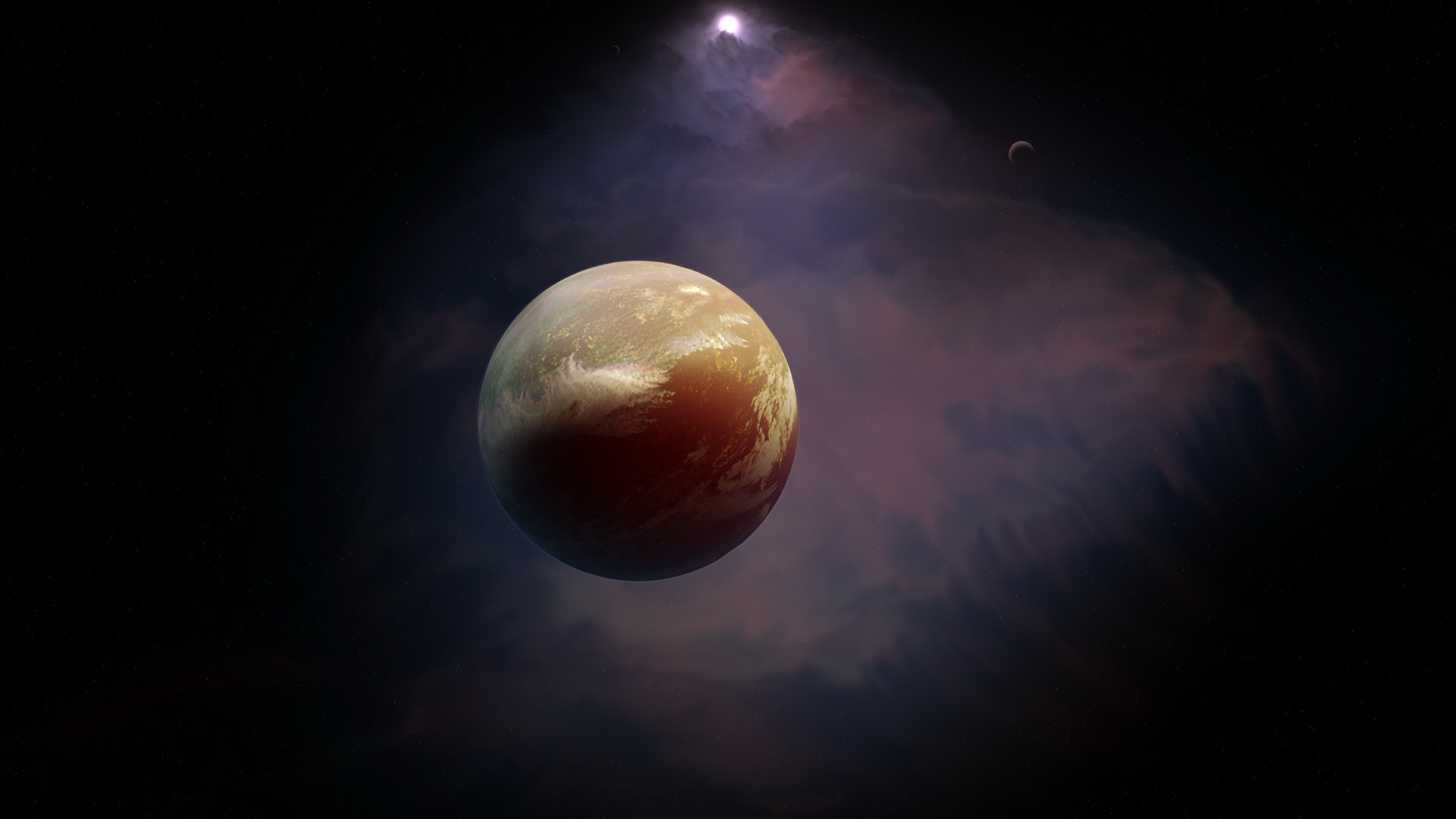日本のIT競争力向上、鍵はユーザー企業自らIT開発できる"省力化・少人材化"
日本のIT競争力向上、鍵はユーザー企業自らIT開発できる”省力化・少人材化”
2021/5/10
日本の機械、電子機器製造業は、世界でもトップクラスの地位にいるが、ITの中心がハードウェアからソフトウェアに移っても、雇用制度などが製造業に最適化されたままであったため、多重下請け構造などの歪みが生まれてしまった。IT開発の省力化、少人材化を進め、ユーザー企業が自身で開発に関与できる環境を整えることが重要になってきている。
1.東芝への買収提案、懸念された技術流出
英投資ファンドCVCによる東芝の買収提案問題は、CVC側が提案を事実上留保したことで一応の決着がついた。本質は経営問題だが、多くの人が心配したのが、日本の技術がまた流出をすることではないかということだ。特に東芝は、原子力や防衛関係の技術を持っており、日本の技術的優位性が失われるだけでなく、国益をも損なう可能性があった。
2016年末に、東芝に巨額損失問題が発生し、NAND型フラッシュメモリなどを製造している半導体メモリ事業を分社化して売却することになった。この株式入札に参加をしたのは、米国のアップル、グーグル、アマゾン、ウェスタンデジタル、台湾の鴻海精密工業、韓国のSKハイニックスなどで、日本企業はいなかった。結局、投資会社を中心にした企業コンソーシアム「パンゲア」が設立され、メモリ事業はここに売却をされ、キオクシアと後に社名変更した。現在は、東芝が株を買い戻し、パンゲア(現キオクシアホールディングズ)の議決権を40%ほど掌握しているが、一歩間違えると、フラッシュメモリの製造技術やノウハウが、他国企業に流出してしまうところだった。
2.世界のITの中心はハードウェアからソフトウェアへ、手持ちの優位性は陳腐化
一方で、同じ時期に新型コロナ接触確認アプリ「COCOA」の情けない状態が報道されている。以前からGitHubなどでも指摘されている単純なバグを放置し、さらにはそもそもテストをまともに行っていないことも明らかになった。
日本は、電子部品ハードウェアに関しては、世界の中で一流国であるものの、技術が流出をし、優位性が失われた。その一方で、ソフトウェアに関してはトップグループに入ることができないままでいる。世界のITの中心が、ハードウェアからソフトウェアに急速に移る中で、手持ちの優位性は流出をし、陳腐化をし、一方で、新しい優位性を作れないままでいる。

3.日本のデジタル競争力ランキング、元から高いとはいえないのが現実
スイスにある国際経営開発研究所(IMD)では、毎年世界各国のデジタル競争力のランキング「IMD
World Digital Competitveness
Ranking」を発表している。これは「知識」「テクノロジー」「将来性」の3つの分野の数値指標を正規化して、総合ポイントの形でランキングをつけるというものだ。2020年の最新版では、日本は世界63ヵ国中27位となっている。
メディアでは、このランキングが低下していることがしばしば報じられるが、IMDの公式ウェブで現在入手できる2013年以降のレポートの順位を見てみると、最高でも20位までしかいったことがない。2017年にも27位になっており、低下したというよりも、元から高いとは言えず、低迷をしているといった状況だ。
レポートの詳細を読むと、日本の課題は「人材の国際経験」「市民のテクノロジースキル」「ビジネスチャンス」「企業の機敏さ」「ビッグデータの活用」などで、いずれも世界ランキング60位前後の最低レベルになっている。
一方で、評価されているのは、「教師、学生の比率」「モバイルブロードバンド利用率」「ワイヤレスブロードバンド普及率」などが世界トップクラスになっている。
4.デジタル競争力はアジアの中でも低迷、20位台を上下
このIMDランキングからアジア各国の順位の推移を抜き出してグラフにしてみた。日本の置かれている地位がよくわかる。
上位国は図抜けているシンガポールの他、香港、韓国、台湾、中国。この上位グループは2018年以降順位を上げている。それに取り残されて20位台を上下しているのが日本だ。グラフを見る限り、上位国に追いつこうとするのはもはや難しいように見える。日本と同じポジションで、順位争いをしているのはマレーシアだ。2020年は、そのマレーシアにも抜かれた。

(IMDのデジタル競争力ランキングの推移。太線が日本で、日本は上位から下落したのではなく、そもそもが低迷をしている。一方で、香港、韓国、台湾、中国はこの数年で順位を大きく上げている。2020年には、日本はマレーシアよりも順位が下となった)
つまり、COCOAの一件は「考えられない失敗」などではなく、日本の実力からしたら、いつ起きても不思議ではない普通のことなのかもしれない。
5.日本のITが抱える課題は「人材の流動性がきわめて小さいこと」
COCOAの失敗の原因は、多重下請け構造と中抜きだとよく言われる。この中抜きとは「何もしないで報酬だけもらう会社がある」という意味で、実際にIT業界にいる方の中には不愉快になったり、異論を口にしたくなったりする方も多いのではないかと思う。日本のITが抱える課題は、そこではなく、人材の流動性がきわめて小さいことが本質だ。
ソフトウェア開発がハードウェア開発と大きく違うのは、開発時には大量のエンジニアが必要となるが、運用のフェーズに入ると少数のエンジニアでよくなるということだ。100人で開発したシステムも、運用は数人で充分になる。かといって、ユーザー企業が、開発時に大量のエンジニアを雇用し、開発が終わったら大量解雇するということはできない。そこで、専門のSIerと呼ばれる開発会社に開発を委託することになる。
この雇用調整が効かないという問題は、開発会社でも同じことで、開発業務を細分化し、人材粒度を小さくした上で、別会社に再委託をする。これを繰り返すことで、日本の雇用制度と雇用調整の問題の折り合いをつけている。そのため、多重下請け構造にならざるを得ない。
ユーザー企業に所属をするエンジニアの割合を国際比較で見ると、日本は圧倒的にユーザー企業に所属をするエンジニアが少ない。IT企業(多くは開発企業)に所属をしているエンジニアが圧倒的なのだ。

(日本のエンジニアの7割以上は、開発企業に所属をする。諸外国は半分以上が、システムを使うユーザー企業が自ら開発をする。「IT人材白書2017」(情報処理推進機構)より作成(Copyright
2017 IPA))
6.ユーザー企業がシステムや業務ツールを自ら開発するメリットとは?
ユーザー企業が自分たちが使うシステムや業務ツールを自分たちで開発することのメリットは、業務に携わっている人や戦略立案をする人の隣で、エンジニアがシステム開発できることだ。業務にしっかりと適合したシステムが開発できる。欧米では、このようにして、ITを事業価値やサービス価値を高める武器として使っている。
一方、日本の場合は、業務と遠いところでシステム開発が行われるため、その企業の業務よりは、業界での標準に合わせたシステムができあがる。事業価値を高めるものを作ることは難しく、アナログ業務をデジタル化するなどの業務効率を高めることが主な狙いになる。しかも、日本は少子化による人材不足という大きな課題を抱えているため、業務の効率化に対する要求も強い。
海外では、ITによってイノベーションを起こすが、日本の場合は現状の業務をデジタル化することに追われ、イノベーションが起こりづらい。これが国際的な競争力を生まれない理由になっている。
このようなことは、業界の人にとっては、わざわざ外から指摘をされるまでもないことで、課題感を感じて、どうにか変えていこうと多くの人が努力をしている。しかし、日本の雇用制度に根を張り、さまざまな仕組みががっちりと噛み合ってしまっているため、なかなか歯が立たないということが大きな苦悩になっている。
同様の多重下請け構造という課題を抱えていたのが建設業界だが、現在は、コンテック(Construction
Tech)などと呼ばれるITの活用で、改善の方向に向かっている。一時は、外国人労働者の活用に活路を求めていた時代もあったが、現在は、機械化とITを積極的に取り入れて、大幅に業務効率を改善し、少ない人数で業務が遂行できるようになってきている。
7.ローコード/ノーコード開発に注目
IT業界にも同じことが言える。開発会社は、ユーザー会社の業務効率化には熱心だが、意外に自分たちの業務効率化は進まない。コードの書き方は、50年前とほぼ同じ手入力で、せいぜいカット&ペーストを活用している程度。テストコードの自動生成もようやく広がり始めたところで、多くの場合、手作業で書いていた。
このような開発企業自身の効率化と、業務に即したシステム開発という2つの課題を解決するものとして、ローコード/ノーコード開発が注目されている。細かいプログラミングの知識がなくても、業務フローの観点からやダイヤグラムやシンプルな命令コードを並べて開発を行うというものだ。
開発企業の業務効率も高くなるが、最も期待されているのは、ユーザー企業自身が自分たちで使うシステム、業務ツールを開発できるようになることだ。業務を行なっている人が自分でツールを開発するので、業務に即したものができあがる。ユーザー企業は、ローコード開発を取りまとめ、サポートする少数のエンジニアを雇用すればよくなる。開発企業は、受託開発をするのではなく、ローコード/ノーコードプラットフォームを開発し、提供する。そういう世界観が期待をされている。
日本の機械、電子機器製造業は、世界でもトップクラスの地位にいる。それが、ITの中心がハードウェアからソフトウェアに移っても、雇用制度などが製造業に最適化されたままであったため、多重下請け構造などの歪みが生まれてしまった。その結果、日本のIT競争力はアジアの中でも中位クラスから浮上することができないでいる。IT開発の省力化、少人材化を進め、ユーザー企業が自身で開発に関与できる環境を整えることが重要になってきている。

原稿:牧野武文(まきの・たけふみ)
テクノロジーと生活の関係を考えるITジャーナリスト。著書に「Macの知恵の実」「ゼロからわかるインドの数学」「Googleの正体」「論語なう」「街角スローガンから見た中国人民の常識」「レトロハッカーズ」「横井軍平伝」など。